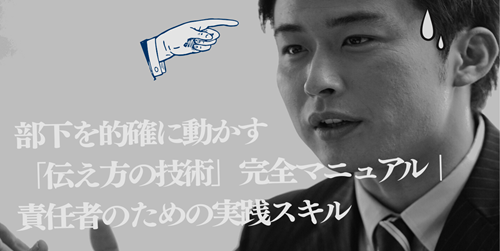「きちんと指示を出したつもりなのに、部下が思うように動いてくれない…」
「伝えたことと違う結果が返ってきてしまう…」
「部下に言ったことがうまく伝わっていない気がする…」
こうした悩みを抱えている責任者は少なくありません。
実は、部下が動かないのは「能力がないから」ではなく、上司の伝え方が不明確なせいであることが多いのです。
この記事では、責任者が押さえておくべき「伝え方の技術」を徹底的に解説します。
目次
【第1章】なぜ部下に指示が伝わらないのか?
まずは原因を理解することから始めましょう。
1. 指示が曖昧すぎる
「早めにやっておいて」「しっかり頼むよ」などの表現は抽象的すぎます。
部下は「いつまでに」「どのレベルまで」仕上げればいいのか分からず、結果的にズレが生まれます。
2. 上司の頭の中だけで完結している
上司はゴールを理解していても、それを十分に説明しないケースがあります。
部下からすると「なぜこの仕事が必要なのか」が分からないため、モチベーションが上がりません。
3. 部下の理解度を確認していない
指示を出して終わりにしていませんか? 部下が本当に理解したかを確認しなければ、勘違いや解釈の違いがそのまま実行に移されてしまいます。
【第2章】部下を動かす「伝え方の技術」5つのステップ
1. 目的を最初に伝える
部下が「なぜその仕事をするのか」を理解すれば、納得して動けるようになります。
📌 例
❌「この資料まとめておいて」
✅「来週の会議でA社に提案するから、そのための資料をまとめてほしい」
「何のためにやるのか」を伝えるだけで、部下はゴールを意識できます。
2. 具体的な「期限・量・基準」を明示する
「早めに」や「しっかり」では伝わりません。
部下に迷いを与えないためには、期限・量・基準を具体的に伝えることが重要です。
📌 例
❌「できるだけ早く準備して」
✅「金曜の正午までに、A社向けの資料を3ページ以内で作成して。図を最低1つ入れて、誰が見ても分かる内容にしてね」
部下がゴールイメージを持ちやすくなり、期待通りの成果が返ってきます。
3. 手順を簡潔に示す(必要に応じて)
部下がまだ慣れていない業務の場合は、手順を示して安心感を与えることも効果的です。
📌 例
「まず過去の提案資料を確認して、その構成を参考にしてみて。必要ならマーケ部に問い合わせて最新データをもらうといいよ。」
ただし、ベテラン部下には細かく指示せず、「任せる部分」を残すことも大切です。
4. 部下に復唱させる(理解確認)
指示の後に「分かった?」と聞くだけでは不十分です。
復唱させることで、理解度を確認できます。
📌 例
「ここまでの指示を、ちょっとまとめて言ってみて」
部下が自分の言葉で説明できれば、内容を理解している証拠です。
5. フォローの姿勢を示す
指示を出した後、「何かあれば相談してね」と伝えるだけで、部下は安心して行動できます。
これは単なる優しさではなく、報連相を促すための仕組み作りです。
📌 例
「もし進める中で分からないことがあれば、すぐに聞いていいからね」
【第3章】伝え方の工夫でさらに部下は動きやすくなる
1. 「WHY→WHAT→HOW」の順で伝える
- WHY(なぜやるのか) …目的や背景
- WHAT(何をやるのか) …具体的なタスク
- HOW(どうやるのか) …進め方や基準
この順番で伝えると、部下は「納得して」「迷わず」「正確に」動けるようになります。
2. 部下のタイプに合わせて伝える
部下の性格や経験に応じて、伝え方を変えると効果的です。
✅ 経験が浅い部下 → 手順を細かく伝える
✅ 経験豊富な部下 → ゴールだけ伝え、やり方は任せる
✅ 慎重な部下 → 安心感を与える言葉を加える
✅ 積極的な部下 → 裁量を与えてチャレンジさせる
3. 曖昧な表現を避ける
上司がよく使いがちな曖昧ワードは、部下を混乱させます。
📌 NGワード集
- 「できるだけ早く」
- 「しっかりやって」
- 「なるべく良いものを」
📌 改善例
- 「〇月〇日17時までに」
- 「数字を必ず入れて、見やすくする」
- 「過去の資料より短く、3分以内で説明できる内容にする」
【第4章】まとめ|責任者が意識すべき伝え方の技術
部下を的確に動かすためには、次の5つのステップを実践しましょう。
1️⃣ 目的を最初に伝える
2️⃣ 期限・量・基準を具体的に示す
3️⃣ 必要に応じて手順を伝える
4️⃣ 復唱で理解度を確認する
5️⃣ フォローの姿勢を示す
さらに、**「WHY→WHAT→HOW」で伝える」「部下のタイプに合わせる」「曖昧な表現を避ける」**といった工夫を加えれば、指示は格段に伝わりやすくなります。
部下が動かないのは、能力不足ではなく、伝え方に原因があることが多いのです。
今日から「伝え方の技術」を実践し、部下が迷わず成果を出せるチーム作りを目指しましょう。